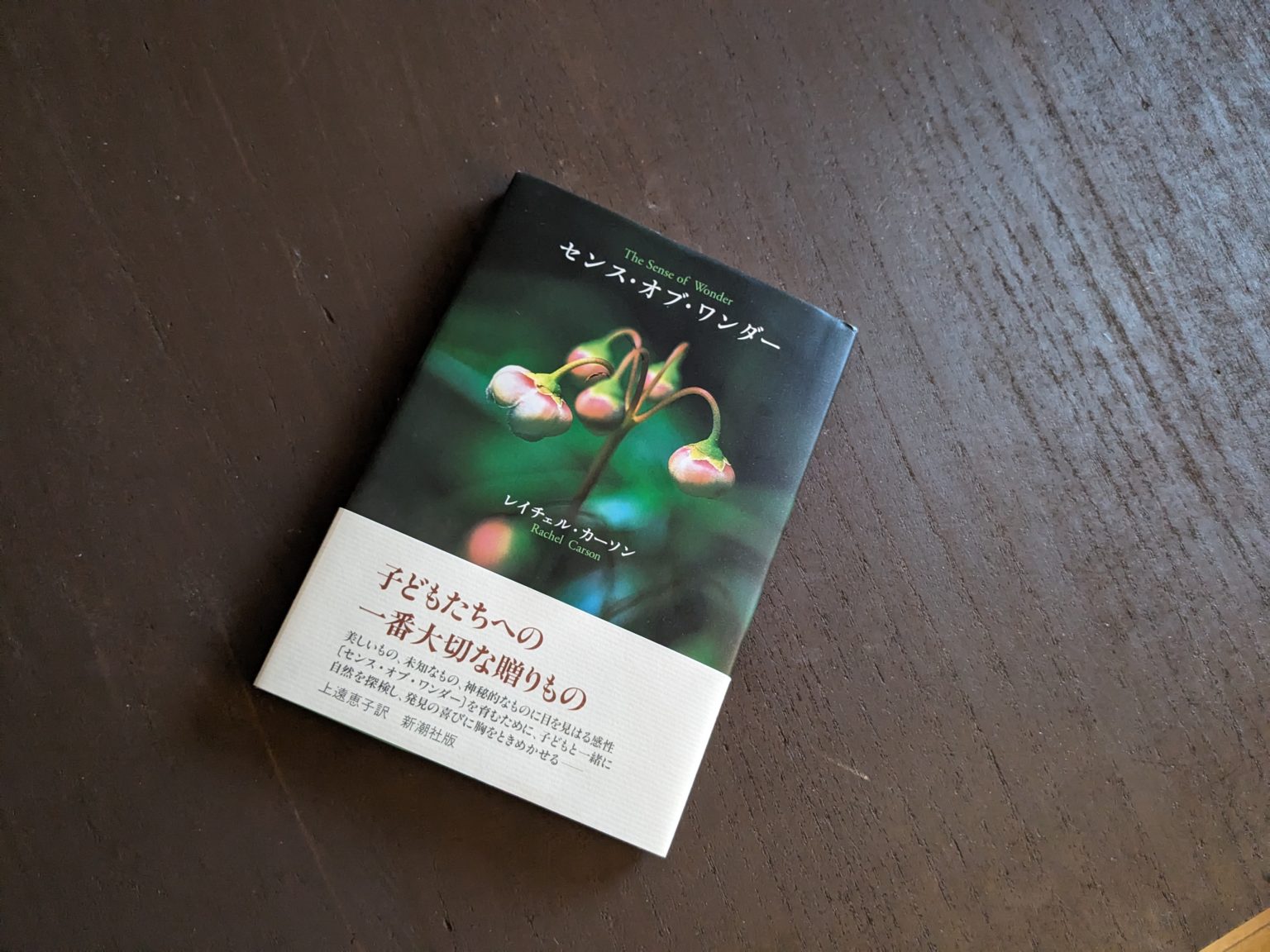ルバーブの紹介と育て方。効能や使い方の参考も。

記事内に商品のプロモーションが含まれる場合があります。
ルバーブの概要
学名 |
Rheum rhabarbarum(親種が不明とされる植物で学名が統一されていない) |
|---|---|
科名 |
タデ科 |
和名 |
ショクヨウダイオウ |
別名 |
セイヨウダイオウ、マルバダイオウ、ガーデン・ルバーブ |
花言葉 |
「迅速 」「忠告 」「快速」 |
開花期 |
6月~7月 |
使用部位 |
葉柄(葉を除いた柄の部分) |
原産地 |
北ヨーロッパ・シベリア |
草丈 |
50cm~150cm |
多年草 |
漢方にカテゴライズされる大横(だいおう)の仲間で、成長するとフキに似た姿を現します。茎が伸びてその先に葉をつけるという一般的な植物の形態ではなく、根に近い地上部から長い柄を持った葉が成長していきます。
薄グリーンの小さな花が集合して咲くのも特徴的です。 葉っぱの直径が60センチほどに大きく茂り、ダイナミックな生長を感じさせる植物で、ヨーロッパでは野生で自生し雑草扱いされることもあるほど。
赤く染まった多肉質な柄の部分には食物繊維やビタミンCが豊富で、生で食すとパリッとセロリのような食感と強い酸味が特徴的で、ジャムにするのが一般的。ビタミンb群、ミネラルも豊富なのでメディカルな側面も期待できます。
ヨーロッパでは朝食にルバーブのジャムが並ぶほどに親しまれています。ムーミンや赤毛のアンなどの物語にも登場するジャムです。 アメリカでは、「パイ・プラント」の愛称で呼ばれ、バイなどに利用される材料としても一般的です。
春先に園芸店に行けば、ハーブエリアに陳列されることも多く、入手しやすくなっているようで日本でも人気のハーブとなっています。
ルバーブの種類
いくつか園芸種がありますが、日本では一般的にルバーブとして流通する苗に明確な品種は明示されてないことが一般的。
種からの栽培に挑戦する場合は品種を意識してみるのも園芸の楽しみのひとつです。インターネットで世界中のルバーブの種を入手できるので探してみてください。
ただ、それほど大きな違いは見られないようです。
ルバーブレッド、ルバーブラバルバロと呼ばれる100cmほどに大きくなるタイプの品種は、赤みと酸味が強く寒冷地向けの品種です。
ルバーブ・ビクトリアは昔ながらの一般的な品種で、長く太い葉柄を収穫できます。
ルバーブに共通するのは基本的に遮光して育てると赤みが強く生育するという点。 これは軟化栽培と呼ばれる光のない環境で生育させる方法で、葉緑素が形成されず、アントシアニンの鮮やかな赤色が優位となります。また。葉柄はより甘みを増すといわれています。
適度に遮光して育てるなどの工夫をすれば赤みが出ますが、まったく色づかない薄緑の品種も多数。
緑色でも風味や酸味が劣るわけではないですが、甘みにこだわるなら挑戦してみるのも良いかもしれません。
ルバーブの主な薬効作用
整腸作用、利尿作用、緩下作用
ルバーブの適用症状
便秘、むくみ、動脈硬化
ルバーブの使い方の参考
料理に
赤い柄の部分を甘く似て、ジャムにします。程よい青りんごのような酸味がジャムの美味しさを際立たせます。
パイやタルト、クランブルなどの焼き菓子にも向きます。ヨーグルト、ドリンクなど、アレンジも無限。
生で細かく刻んでドレッシングに加えても美味しく味わえますし、サラダのアクセントにしても映えます。
ティーとして
ドライにした葉柄の部分をティーにするのも一般的。デトックス効果や整腸作用が期待され、便秘の解消などをサポートしてくれるそう。
ルバーブの育て方と収穫

ハーブの基本の育て方(有機&無農薬)
好む環境
日当たりと水はけが良い、涼しい場所を好む。温帯地域の日本では育てやすいが梅雨が難点。冷涼地での栽培が容易で北海道などは特に適しているといえる。
涼しい春と秋の気候はルバーブが大好きな気候。
種蒔き&育苗
生育適温は10℃~18℃と低めなのに、発芽適温は25℃と高めなので、春先などの寒さが残る時期なら温室空間などで育苗ポットに種まきする。
本葉が2~3枚になったら間引きして一株にする。 夏の終わりなら露地でも発芽する。
種からだと一年目は葉が数枚しか育たないので、収穫できるのは二年目以降から。早く収穫したい場合は苗からの栽培が推奨。
定植
本葉が3~4枚になったら、定植の時期。地植えが推奨されるほど大きく育つ植物だが、プランターで育てる場合は10~15号鉢に定植する。
地植えの場合は株間隔は30cm程度。大株にするなら100cmほど空ける。水はけが良くなるように高畝にして植えるとgood。
直根性のため、根鉢は崩さす優しく育苗ポットからだし、そっと植え付けるようにしたい。
大きな葉が特徴的な植物なので、泥などが跳ねると病気の原因にもなりやすい。藁などで株元を覆うと病気の予防になるので、余裕があれば施すと良い。
土
肥沃な弱アルカリ性の土を好み、ハーブ培養土よりも野菜培養土などの肥料分が多い土が生育を促してくれる。
地植えの場合は前もって苦土石灰などを混ぜ込んで土づくりをしておく。
肥料
定植時にしっかりと元肥を与え、定植後一か月目からの収穫期までは液肥を月一回程度を与えるようにすると大きく成長。
日当たりと場所
日光がよく当たる風通しの良い場所が適している。水を与えたら、さっと水がはけていくような場所が理想。陰になりやすい場所は避けて。
水やり
過湿は嫌うので、表土が乾いたらたっぷりの水を底から滴り落ちるほど与え、メリハリをつけるようにする。乾燥しすぎるのも生育を鈍らせるので注意。葉が大きく茂ってくるので水やりの頻度は多くなる。
病害虫
ヨトウムシやコガネムシなどがやってきて葉を食べてしまうのは一般的な食害ですが、ある程度なら葉は食べないのでおおらかに構えて。見つけたら慌てず捕獲を。
ただ、新芽が食害されると生長に悪影響なので、よく観察して日ごろから心掛けたい。
自然農薬などで予防しておくのも大切。過湿が続くと、うどん粉病などの懸念されるため、梅雨時期から夏場は特に注意。
夏に意識したいポイント
耐暑性は低く、日向を好むが夏の高温は大の苦手。夏の西日に特に注意し、適度に遮光できる場所に移動して(プランターの場合)風の通る場所で夏を越せると秋まで収穫できる。日光が強いと赤い葉柄の部分が緑色になる。また、しおれて場合によっては枯れてしまうこともあるので注意。
冬に意識したいポイント
耐寒性はあるので、冬を越すのは容易だが、-3℃~ー4℃程度で地上部はほとんど枯れる(特に寒冷地)根は生きているので、適度に水を与えて根を枯らさなければ、春先にまた芽吹く。
収穫
収穫は5月から10月中旬までできる。種からの場合は二年目以降。葉柄が30cm程度から収穫可能。2~3本もあればジャムにするには十分な量。
露地の場合は長雨の時期は株が弱るので、その前に収穫して加工してしまうのも選択肢のひとつ。生のまま冷凍保存もできるので日本の梅雨時期は臨機応変に。
長く収穫するために花穂が出たら摘蕾する。そのまま育てて秋に種を採取するのも良い。長く楽しむために一度に刈り取らず、半分程度残しておいて秋に楽しむのもひとつ。
※三年以上長く育てている株は春先(3月~4月)に株分けで増やし、株を更新すると良い。 新芽がたくさん芽吹いてきたころに、最低一つ以上の新芽を残しながら根をカットして株分けするようにする。 こぼれ種でも容易に増えるので毎年楽しめる。
※大きくなりすぎると簡単に折れてしまうので、適切なタイミングで収穫して利用することを心掛けたい。
※春先に出てくる花芽は早めに摘み取り、大きく育ててたくさん収穫できるようにしたい。
ルバーブのよもやまエピソード
インドの世界の最古最大の長寿の科学であるアーユルヴェーダでは、宿便の排出を促し、大腸を整える作用が期待できるとされ利用頻度の高い植物です。
葉にはシュウ酸が含まれるので食用は避けますが、煮出した溶液は銅や真鍮の研磨用に使われることもあるようです。知っておくとアンティーク用品のお手入れに利用できそうです。
古代ギリシャ語でルバーブは「蛮族」を意味する言葉に由来するとされ、野性的な印象を抱かせます。他にも流れるという意味を持つ言葉も由来の一つとして挙げられ、下剤として利用できる整腸作用と関連しているという説も。
食用品種のルバーブは種間雑種であり、原種が特定されていない神秘的な側面も持ちますが、栽培品種としてはイギリスが発祥とされています。
Today's moon
欠けていく月前半
月齢=17.4

月星座=蠍座→射手座
月の力もチェック▶
Newpost

韓国風豆腐のチョリム丼
お豆腐を甘辛い調味液で煮て、ご飯に乗せてどんぶりにし…...more

無秩序な秩序と多様性
「尊重する」というのは、前提に理解がないと成立しない…...more

4月22日はアースデイ。地球に何を思う?何を届ける?何を祈る?地球を祝福しよう。
毎年、4月22日はアースデイ(地球の日)とされ、世界中で…...more

桜を塩漬けで保存、春よ…もう少しだけ
咲いたと思ったら束の間、あっという間に散っていく桜。…...more
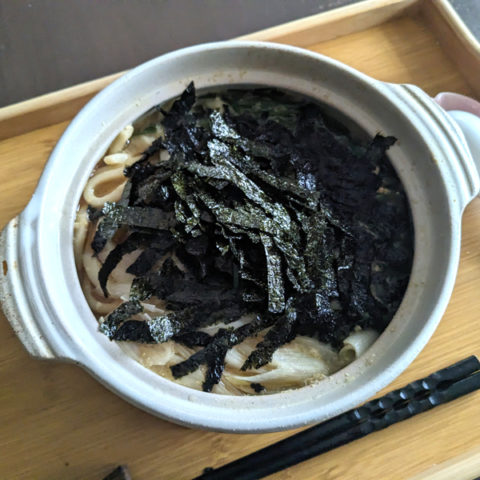
すぐおいしい!インスタント海苔わかめうどん
15分でできる、インスタント感覚で作れるうどんです。海…...more

お花見の魔法で叶う!願いも祈りも、精霊の後押しで。
桜が咲く季節のアクティビティで、お花見は定番ですが、…...more
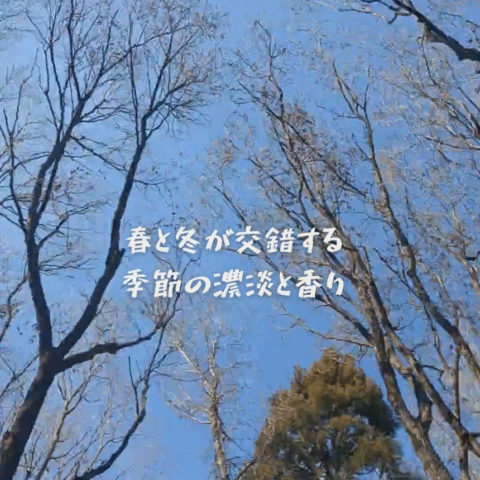
春と冬が交錯する季節の濃淡を味わう。今、ここを感じるお散歩。
左脳が優位すぎるとあれができていない、これをしなくち…...more

酵素ジュースを自家製で愉しむ。旬の恵みをぎゅっと詰めこんで。
酵素と言えば、美肌や腸内環境の改善、ダイエットサポー…...more